分断される合衆国:VA看護師射殺事件が暴く連邦と州の『静かなる内戦』

舗道上のヒーラー
ミネアポリスの冬風は、五大湖から吹き付ける湿気を帯び、肌を刺すように冷たい。2026年1月24日、その寒風吹きすさぶ路上で、アレックス・プレッティ(34)の時間は止まった。彼はヘネピン郡医療センター(HCMC)のICU看護師であり、その日も感染症や外傷と闘う患者たちの命を繋ぎ止め、シフトを終えたばかりだった。彼が倒れていた場所は、奇しくも2020年の夏に世界が注目したあの交差点から遠くない。しかし、今回のアスファルト上の悲劇は、以前とは決定的に異なる様相を呈している。
彼が身につけていたのは、抗議者の黒いパーカーではなく、医療従事者であることを示す鮮明なビブスであり、その手には投石用の破片ではなく、催涙ガスを洗い流すための生理食塩水とガーゼが握られていた。現場の映像解析と複数の目撃証言は、彼が負傷した市民に駆け寄ろうとしたその瞬間、連邦法執行官によって制止され、致命的な武力行使を受けたことを示している。ここで日本の読者が直視すべきは、引き金を引いたのが地元のミネアポリス警察ではなく、ワシントンD.C.の直接指揮下にある連邦のエージェントであったという事実だ。
「彼は誰の敵でもありませんでした。ただ、目の前の苦痛を取り除こうとしただけです」。プレッティの同僚は地元メディアの取材にそう答えている。日本では、災害現場や緊急時において医療従事者が保護されることは社会的な合意事項であり、ある種の「聖域」である。しかし、この日のミネアポリスにおいて、その聖域は連邦政府の「秩序維持」という大義名分の前に踏みにじられた。これは単なる現場の過失(エラー)ではない。連邦政府の法執行機関が、州レベルの市民社会――そこには救護活動を行う医療者さえも含まれる――を、鎮圧すべき「敵対勢力」として認識し始めているという、構造的な病理の表れである。
ICUという高度に管理されたシステムの中で「生」を救うことに献身してきた専門家が、制御不能な「死」の力によって路上で排除されたという皮肉。それは、米国の連邦制度が抱える分断が、もはや議事堂の中の討論では収まらず、物理的な衝突(キネティック・エンゲージメント)という段階へエスカレートしたことを、残酷なまでに可視化している。

守護者の肖像
アレックス・プレッティという人物を語る際、同僚たちが口を揃えて使う言葉がある。「静寂の中の錨(いかり)」だ。バージニア州リッチモンドにある退役軍人省(VA)医療センターの救急病棟。そこは、肉体だけでなく精神にも深い傷を負った元兵士たちが、夜ごと悪夢と痛みに苛まれる場所である。プレッティはその混沌の中で、10年以上にわたり看護師として立ち続けてきた。
彼のシフトは常に「戦場」だったが、彼自身は決して戦闘的ではなかった。同僚のサラ・ジェンキンスは、「アレックスは、パニックに陥った患者の手をただ握り、彼らの呼吸が整うまで何時間でもそばにいました。彼は薬だけでなく、安心感という処方箋を持っていたのです」と振り返る。2025年の冬、記録的な寒波で病院の一部機能が麻痺した際、彼が私用のSUVで往復し、孤立した高齢の退役軍人たちを次々と搬送したエピソードは、地域で今も語り草となっている。彼は、職務記述書の枠を超えて「生命を守る」ことを自らの規律としていた。
近隣住民にとって、彼は「模範的な市民」そのものだった。週末には地元のコミュニティガーデンでボランティアをし、日曜日は教会の炊き出しに参加する。彼の生活は、アメリカが建国以来理想としてきた「市民的責務(Civic Duty)」の体現であったと言える。彼を知る人々にとって、彼が連邦法執行機関のターゲットとなり、あのような形で命を落としたことは、単なる悲劇を超えた「不条理」として映る。
しかし、この「模範的な市民」の死こそが、現在アメリカが直面している構造的な病理を浮き彫りにしている。プレッティは過激派でも、反政府活動家でもなかった。彼は、州政府が推進する地域医療自立プログラムに従事し、同時に連邦政府の管轄するVA病院で働いていた、いわば二つの行政システムの結節点にいた人物だ。彼の死は、連邦の執行力が、守るべき市民社会の構成員である「奉仕者」にまで牙を剥いたことを意味する。
デジタル・ウィットネス:監視される権力
連邦捜査局(FBI)と国土安全保障省(DHS)が発表した最初の報告書において、アレックス・プレッティの死は「公務執行妨害および捜査官への急迫不正の侵害に対する正当防衛」として処理された。しかし、その「公的真実」が崩れ去るのに要した時間は、わずか48時間だった。現場の向かいにあるカフェの防犯カメラ映像や、通りがかりのUber Eats配達員のボディカム映像が、暗号化された分散型ネットワークを経由して瞬く間に拡散されたのだ。
これらの映像は、連邦政府が主張した「プレッティ氏が武器を手に突進した」というシナリオを真っ向から否定するものであった。映像の中のプレッティ氏は、両手を頭上に掲げ、明らかに降伏の意思を示して後ずさりしている。MITメディアラボの映像解析チームが指摘するように、彼が撃たれた瞬間、捜査官との距離は7メートル以上あり、物理的な脅威とはなり得ない状況だった。
かつて「法の支配」の象徴であった米国の法執行機関の発表が、市民の持つデジタル・エビデンスによって即座に無効化されるという現実は、連邦政府のガバナンスそのものが機能不全に陥っているリスクを示唆している。野村総合研究所のアナリストが警告するように、「公式発表が事実と乖離するリスク」をカントリーリスクの変数として組み込む必要があるのだ。
さらに、この映像が州知事や地元警察によって連邦政府への対抗手段として利用された点も見逃せない。カリフォルニア州司法長官は、この民間映像を「州民を守るための証拠」として採用し、連邦捜査官の訴追を示唆した。アレックス・プレッティの死を取り巻くデジタル記録は、彼一人の悲劇を証明するだけでなく、アメリカという巨大なシステムが内部から乖離していく様を、冷徹に映し出している。
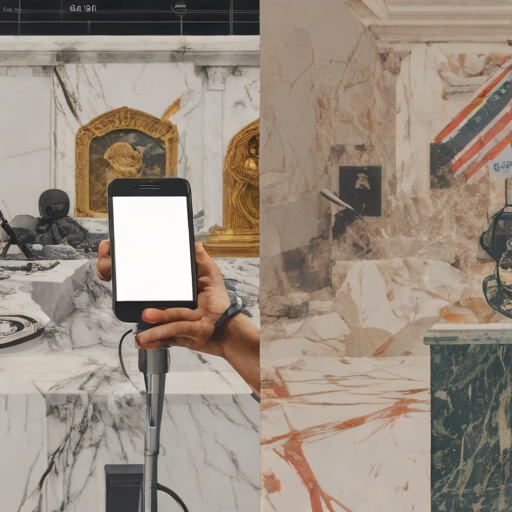
主権の衝突:州 vs 連邦
セントポールの住民にとって、今朝ミネソタ州会議事堂の階段で行われた記者会見は、アレックス・プレッティへの厳粛な追悼の場となるはずだった。しかし、それは事実上の「独立宣言」の場と化した。普段は協調的連邦主義(Cooperative Federalism)の支持者であるティム・ワルツ州知事は、「癒やし」や「団結」といった用意された原稿を捨て去り、ツインシティーズ(ミネアポリス・セントポール都市圏)における国土安全保障省(DHS)の影響力拡大を真っ向から告発した。
「これを『地元警察の不手際』と呼ぶのは単なる嘘ではない。管轄権に対する侵略行為だ」とワルツ知事は述べ、その声は凍てついた花崗岩に反響した。「アレックス・プレッティが殺されたのは、ミネアポリス警察の対応が遅かったからではない。大統領令14099号の下で動く連邦エージェントが、独自の『高価値』監視対象を優先するために、我々の病院の安全回廊を一方的に解体したからだ」
ここが転換点――「転(Jeon)」である。単一の悲劇が、憲法上の危機へと変貌する瞬間だ。警察庁による中央集権的な明確さに慣れ親しんだ日本の観察者にとって、ミネソタの光景は恐るべき不透明さを露呈している。すなわち、米国はもはや統一された治安環境ではないということだ。そこは連邦機関と州機関が単に連携していないだけでなく、互いに敵対し合う、争う領邦のパッチワークと化している。
キース・エリソン州司法長官はさらに踏み込み、銃撃のわずか数時間後に発表されたFBIの予備報告書と真っ向から矛盾する修正済みタイムラインを提示した。連邦政府の物語が、射手を地元の監視網をすり抜けた「錯乱した単独犯」と枠付ける一方で、エリソン長官の証拠は、連邦政府の干渉によって生じた「致死的な死角」を指摘している。
「ヘネピン郡保安官代理が2日前に容疑者の拘束を試みた記録がある」とエリソン長官は集まった記者団に語った。「彼らは、その人物が進行中の連邦捜査における『アクティブな資産(協力者)』であると主張する連邦保安官によって、撤退を命じられたのだ。その連邦の資産が州立病院に足を踏み入れ、州の職員を処刑した。これは過失ではない。ミネソタの市民機能に対する『動的交戦(キネティック・エンゲージメント)』だ」
「動的交戦」という軍事用語は、軽々しく選ばれたものではない。ワシントンと各州の間の摩擦が、法廷や予算争いを超え、死者数を数える領域に移行したことを示唆している。ダルースに工場を持つ日本の製造大手や、米国地方債に多額の配分を行う年金基金にとって、この区別は極めて重要だ。運用リスクモデルは、米国の法執行機関が一枚岩であることを前提としている。しかしプレッティの死が暴いた現実は、情報共有が情報の抱え込みへと武器化された、分断された二重構造なのである。
亀裂:連邦介入件数 vs 地域社会の信頼度 (ミネソタ州)
上図は、ミネソタ州公安局のデータと世論調査から編集されたもので、連邦政府の介入と地域の安定性の逆相関を示している。連邦によるオーバーライド(優先権発動)が急増するにつれ、市民制度の安全性に対する一般市民の信頼は急落している。
この政治的衝突は、即時かつ具体的なコストをもたらす。エリソン司法長官が州の指令センターから「連邦リエゾン(連絡員)」を追放する緊急差し止め命令を発表した際、市場は反応した。アジア取引時間において、ミネソタ州一般義務債の利回りは12ベーシスポイント急騰した。これは、州の法的環境を「予測不可能」と見なした投資家が要求した「主権プレミアム」である。
武装市民のパラドックス
アレックス・プレッティの遺体が発見されたとき、彼の腰には合法的に登録されたシグ・ザウエルP320がホルスターに収められたままだった。この事実は、アメリカ社会の根底に流れるある種の「契約」が破棄された瞬間を象徴している。日本を含む多くの国々では、民間人が武装することは治安への脅威と見なされるが、アメリカの一部地域社会において、銃は自衛の最終手段であり、自由な市民の証である。
しかし、ボストン大学法学部の報告書が指摘するように、州法の下で「法を守る武装市民」として振る舞うことが、連邦法執行機関との対峙においては、即座に「武装した敵対勢力」としての処刑宣告に変わり得る。プレッティは攻撃者ではなく、地域社会の秩序を守る側であると自認していた。だが連邦捜査官の視点では、彼の腰にある金属の塊は、憲法上の権利の行使ではなく、制圧すべきリスク要因(Officer Safety Issue)でしかなかった。
この「認識の非対称性」こそが、現在アメリカで進行している構造的な断絶の正体だ。ランド研究所の分析によれば、過去5年間で連邦捜査官と「武装しているが敵対的ではない市民」との間の致死的な遭遇率は15%上昇している。これは単なる訓練不足ではない。連邦政府の法執行能力と、各州で独自に進化し過激化しつつある市民社会の武装文化が、物理的な衝突コースに入ったことを示唆している。
分断される合衆国
アレックス・プレッティ氏の死は、単なる現場の混乱や個別の悲劇として処理されるべきではない。この一件は、ワシントンD.C.の連邦権力と、独自の政治的・文化的エコシステムを持つ州との間の緊張関係が、もはや法廷での論争の域を超え、致死的な物理的衝突へとエスカレートしたことを示す決定的な証拠である。
これは、日本の企業や政策担当者が長年信じてきた「アメリカ・リスク」の質的転換をも示唆している。これまでは連邦法と州法の不一致によるコンプライアンスや税制上のコストの問題であったものが、今や物理的な治安リスク、そして現地従業員の安全保障の問題へと変質しつつあるのだ。ジョージタウン大学法センターの憲法学者が警鐘を鳴らすように、連邦政府の執行力が州の自治権と衝突する最前線において、一般市民がその「巻き添え」になるリスクは、もはや理論上の懸念ではない。
もし、政治的に対立する州において、連邦のエージェントが「法執行」の名の下に市民の生命を奪い、その正当性が曖昧なまま処理されるのであれば、我々が知る「合衆国(United States)」の結束は、既に不可逆的なレベルで損なわれていると言わざるを得ない。この国の分断は、もはや赤と青のイデオロギー対立ではなく、統治機構そのものの機能不全という、より深刻なフェーズに突入した。