[2026年水道問題] 料金再値上げの深層:老朽インフラ更新と持続可能な水循環への投資
![[2026年水道問題] 料金再値上げの深層:老朽インフラ更新と持続可能な水循環への投資](/images/news/2026-01-29-2026--9nr14.png)
請求書に刻まれた『2026年問題』
郵便受けに届いた一枚の検針票が、地方都市に住む高橋美咲氏(42歳・仮名)の日常に小さな、しかし無視できない波紋を広げた。2026年4月分の水道料金請求額は、前年同月比で約18%の上昇を示していた。「物価高で食費や電気代が上がるのは覚悟していましたが、まさか水までもがこれほど上がるとは」。彼女が直面しているのは、個別の家計の問題にとどまらず、日本列島全体を静かに、確実に覆い尽くしつつある「2026年問題」の氷山の一角に過ぎない。
2026年度、全国の自治体の約4割が水道料金の改定に踏み切った。これは、厚生労働省がかねてより警鐘を鳴らしていた「人口減少による収益減」と「高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化」という二重の構造的要因が、限界点に達したことを意味する。これまで多くの自治体は、住民生活への影響を懸念し、一般会計からの繰入金などで赤字を補填しながら料金を据え置いてきた。しかし、第2次トランプ政権下の経済政策に端を発する円安基調に伴うエネルギーコストの上昇や、資材価格の高騰が追い打ちをかけ、もはや「先送り」という選択肢は消滅したのである。

特に深刻なのは、給水人口が減少傾向にある地方自治体だ。日本水道協会の試算によれば、現状の水道管更新ペース(年間約0.6〜0.7%)では、すべての管路を更新するのに130年以上を要するとされている。法定耐用年数である40年を大幅に超えた水道管が地中に眠り続けている現状は、いつ大規模な漏水事故や断水が発生してもおかしくない「時限爆弾」を抱えているに等しい。私たちが支払う料金の増額分は、蛇口から出る水の対価というよりも、この老朽化した血管網を維持し、次世代へと繋ぐための「安心への投資」という側面を強く帯びている。
全国水道管の老朽化率と更新率の推移 (出典: 厚生労働省・日本水道協会データより推計)
しかし、この「投資」に対する納得感を醸成するのは容易ではない。元自治体職員の鈴木健一氏(65歳・仮名)は、「かつては水道事業といえば黒字が当たり前だった時代もあった。なぜこれほどの急激な負担増が必要なのか、具体的な経営改善の努力が見えにくい」と指摘する。実際に、隣接する自治体間でも料金格差が数倍に広がるケースが散見され、広域化による効率化が進んでいない地域では、住民の不公平感が募っているのが実情だ。
更新されない水道管:足元で進行するインフラ危機
日本の水道インフラは今、静かなる崩壊の危機に瀕している。私たちが蛇口をひねれば当たり前のように手に入る「安全な水」の背後には、高度経済成長期に集中的に整備された膨大な管路網が存在する。しかし、1960年代から70年代にかけて敷設されたこれらの水道管の多くが、法定耐用年数である40年をとうに過ぎ、物理的な限界を迎えつつあるのだ。
かつて「水と安全はタダ」と言われた日本の神話は、足元から崩れ始めている。厚生労働省の推計によれば、すべての老朽管を更新するには今後数十年で天文学的な投資が必要とされているが、実際の更新ペースは遅々として進んでいない。地方都市で水道事業の維持管理に携わる鈴木健一氏(52・仮名)は、現場の窮状を次のように語る。「毎年のように漏水事故が発生していますが、それは氷山の一角に過ぎません。予算の制約から、緊急性の高い箇所を『対症療法』で修繕するのが精一杯で、抜本的な管路の更新には手が回らないのが実情です」。鈴木氏の言葉は、多くの自治体が抱える共通の悩みを代弁している。
さらに2026年現在、この問題はより複雑な経済的要因と絡み合っている。建設資材の高騰と慢性的な人手不足である。特に、熟練した配管工の高齢化と減少は深刻で、資金があっても工事を請け負う業者が確保できないという「供給制約」が顕在化している。この構造的な「更新費用の増大」と「収益の減少」の挟み撃ちこそが、全国的な水道料金値上げラッシュの真の要因である。
水道管の経年化率と更新率の推移 (出典: 厚生労働省・国土交通省資料より推計)
『ゾンビニュース』に惑わされないために
SNS上のタイムラインを流れる「水道料金が3倍になる」というセンセーショナルな見出しを目にしたことはないだろうか。2026年に入り、全国各地で料金改定が実施、あるいは議論される中で、こうした不安を煽る情報は後を絶たない。しかし、情報の出所を冷静に辿ると、その多くが2024年以前に作成された古い試算や、最悪のシナリオを前提としたシミュレーションに基づいていることが判明する。これらは実態と乖離したままネットの海を彷徨い続ける、まさに「ゾンビニュース」である。
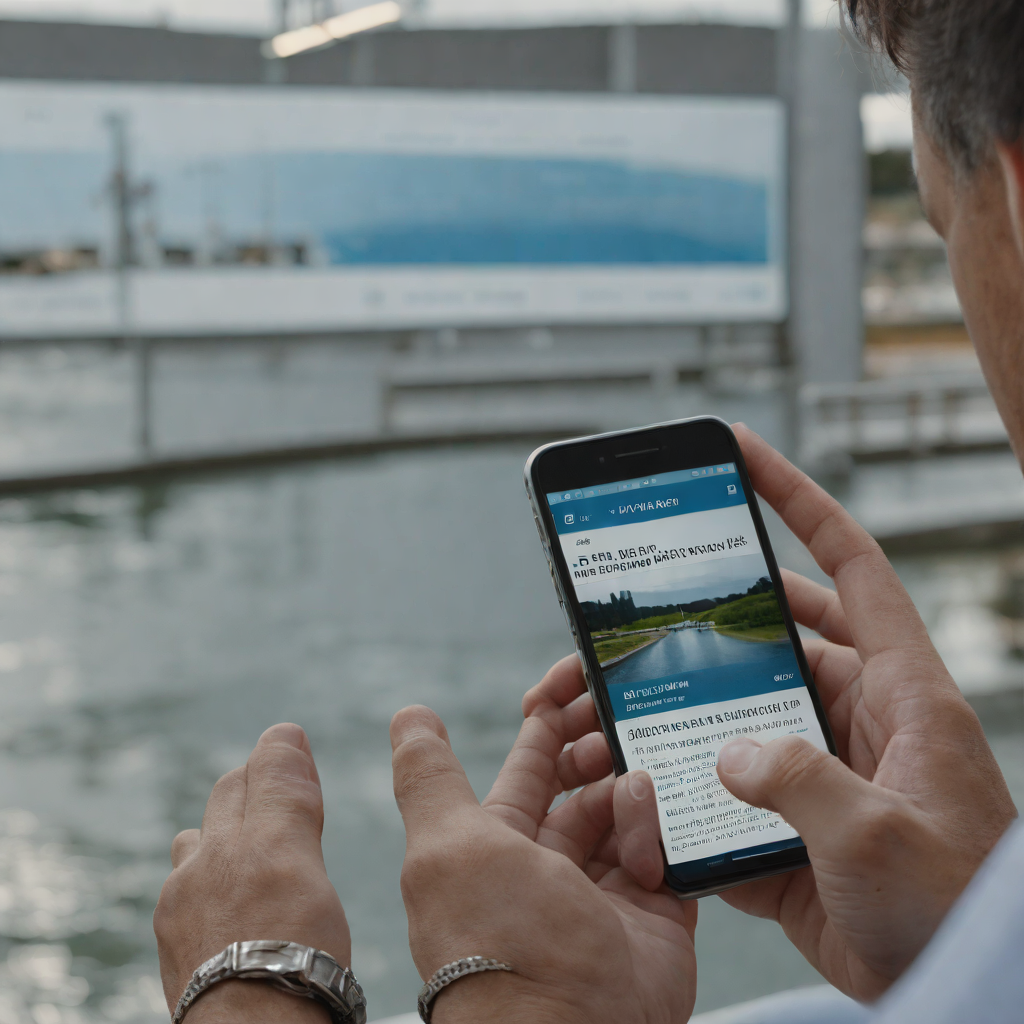
東京都内のマンション管理組合で理事を務める鈴木氏は、先月、居住者向けの掲示板アプリに投稿された「来月から水道代が急騰する」という書き込みに翻弄された一人だ。彼が慌てて水道局の公式サイトを確認したところ、実際の改定幅は記事にあるような「倍増」ではなく、段階的な12%の引き上げに留まっていた。彼が目にした情報は、インフレ率が現在とは異なる前提で2023年に書かれたオピニオン記事の再拡散だったのである。
なぜ、こうした誤情報が2026年の今、再び拡散力を持ち始めているのか。社会情報学を専門とする早稲田大学の田中浩二教授(仮名)は、「生活防衛意識の高まりが、確証バイアスを強化している」と指摘する。円安と物価高が常態化する中、人々は「悪いニュース」に対して敏感になっており、情報の鮮度を確認するプロセスを飛ばして「やはり来たか」と受容してしまう傾向があるという。重要なのは、SNSで回ってくるショッキングなデータを鵜呑みにせず、そのデータの「賞味期限」と一次情報を確認することだ。
漏水という『見えない税金』
蛇口を捻れば清浄な水が出る。この「当たり前」の対価として支払われる水道料金の中に、実は消費者の元へ届くことのない水のコストが含まれている事実は、あまり意識されることがない。それが「有収率」の裏返しである漏水率、すなわちインフラの老朽化によって失われる水の問題である。
厚生労働省の統計によると、全国の水道管の約20%が法定耐用年数である40年を超えているとされ、この数値は地方部において特に顕著だ。老朽化した管からの漏水は、単なる資源の無駄遣いにとどまらず、浄水処理や送水ポンプにかかるエネルギーコストまでもが、誰にも使われることなく地面へと消えていることを意味する。これを経済的な視点で見れば、我々は「使った水」だけでなく、「失われた水」のコストまでをも「見えない税金」として料金に上乗せされ、負担している構造にある。
事業規模別・平均無収水率(推定値)出典:国土交通省・厚生労働省関連資料より推計
このような状況下で、単に「老朽化対策のため」という大義名分だけで料金改定を行うことは、住民の理解を得る上で十分とは言えない。「安心」という日本の水道が誇るべき価値を守るためには、漏水調査へのAI導入や、スマートメーターによる早期発見など、テクノロジーを活用したコスト削減の道筋を具体的に示す必要がある。
広域化と民営化の是非:持続可能なモデルを求めて
人口減少とインフラの老朽化が同時に進行する「複合危機」の中、単独の自治体による水道事業の維持が限界を迎えつつあることは論をまたない。そこで浮上するのが、近隣自治体と事業を統合する「広域化」と、民間企業のノウハウを活用する「コンセッション方式(運営権の民間売却)」という二つの選択肢である。
広域化は、複数の自治体が浄水場や管路を共同利用することで、スケールメリットを追求する手法だ。しかし、その実現には高いハードルが存在する。地方都市の水道局で30年以上勤務する山口博史氏(仮名)は、「隣接する自治体同士でも、過去の投資額や借金の額、料金体系が異なるため、『不公平感』の解消が最大の難所」と語る。
一方、より抜本的な経営改革として注目されるのがコンセッション方式だ。推進派は、民間企業の調達力によるコスト削減や技術革新のスピードをメリットとして強調するが、水道という「生命維持インフラ」を市場原理に委ねることへの懸念は根強い。海外では再公営化の事例もあり、日本国内においても、災害時の対応や過疎地域へのサービス維持といった「公共性の担保」に関する議論が続いている。
結局のところ、重要なのは事業主体が行政か民間かという二元論ではなく、適切な投資が行われ、水質と供給が守られているかを監視できるガバナンス体制の構築にある。我々利用者は、請求書の金額に一喜一憂するだけでなく、その対価が「20年後の安心」に対して支払われているかという厳しい目を向ける必要がある。