[製品安全] 警告文の死角とアフォーダンス:食品模倣コスメが突きつける2026年の倫理的課題
![[製品安全] 警告文の死角とアフォーダンス:食品模倣コスメが突きつける2026年の倫理的課題](/images/news/2026-01-29--2026-7my3np.png)
誤認必至の「棚」:日常に潜む甘い罠
ドラッグストアの整然と並ぶ棚の中で、その境界線はかつてないほど曖昧になっている。UHA味覚糖の人気グミ「コロロ」のパッケージを、形状、色彩、そして開封時のジッパーの位置に至るまで徹底的に再現したハンドクリームが店頭に並んだ時、消費者が抱いたのは「可愛らしさ」への共感よりも、本能的な「危うさ」への警戒心だった。この製品は、マーケティングにおける「遊び心」が、消費者の安全を支える「認知的信頼」を侵食し始めた象徴的な事例と言える。

デザイン心理学において、物体が持つ形状や色が人間に特定の行動を促す性質を「アフォーダンス」と呼ぶ。瑞々しい果実の写真と、一口サイズのパウチ。これらが組み合わさった時、人間の脳は意識的な思考を経る前に「これは食べ物である」という指令を出す。たとえパッケージの隅に「これは食べ物ではありません」という警告文が記されていたとしても、視覚情報が持つ直感的なアフォーダンスは、言語による注意喚起を容易に上書きしてしまう。
実際に、都内のドラッグストアで買い物をしていた高橋宏氏(仮名)は、危うくこの製品を孫のために購入しそうになったと語る。「グミの新作だと思って手に取りました。レジに持っていくまでハンドクリームだとは気づかなかった。もし子供が一人でこれを見つけたら、迷わず口に入れていたでしょう」。高橋氏が感じた恐怖は、決して個人の注意力の問題ではない。2025年に実施された消費生活科学研究所の調査によれば、食品を模倣した雑貨における「警告文の認知率」は、パッケージ全体のデザインが持つ「食品としての既視感」に阻まれ、わずか20%以下に留まるという結果が出ている。
視覚情報とテキスト情報の認知優先度(Source: 2025年消費生活科学研究所「製品安全とアフォーダンス」調査)
2026年現在、トランプ政権下の米国では規制緩和の波が押し寄せ、市場の自由競争が再評価されている。しかし、その影響が波及する日本国内においても、こと「身体の安全」に直結する製品デザインについては、規制のあり方を再定義すべきだという声が強まっている。企業の社会的責任(CSR)が、単なる環境配慮から「認知的な安全性の担保」へと拡大している中で、マーケティングの自由と公共の安全のバランスは、今まさに崩れようとしている。
「映え」の代償とSNS経済の影
SNSのタイムラインで一瞬のうちに消費者の目を奪わなければならない現代のマーケティングにおいて、UHA味覚糖のグミ「コロロ」と粧美堂が展開したコラボレーションは、企業側から見れば「視覚的な勝利」だったのかもしれない。しかし、その勝利は公共の安全という前提を置き去りにした脆い成功の上に成り立っている。2020年代半ば、特にトランプ政権下での過度な規制緩和がグローバルな潮流となった2026年現在の小売市場において、単なる機能性よりも「ネタ消費」や「パケ買い」を誘発するビジュアルのインパクトが、売上を左右する最大の因子となっている。
都内のデジタルマーケティング会社で戦略立案に携わる佐藤健太氏(仮名)は、近年の商品開発の傾向を次のように指摘する。「SNSでのインプレッション(閲覧数)が通貨となった現代、企業は広告費をかけずに拡散される『違和感』を意図的に作り出しています。コロロのパッケージをそのまま流用したハンドクリームは、消費者の既視感を利用して認知コストを下げ、SNSでの二次拡散を確実にするための、計算され尽くした戦略です」。しかし、そこにはブランドの認知度を「安全の保証」と錯覚させる危険な罠が潜んでいる。

この戦略が抱える最大の問題は、前述した「アフォーダンス(行為の誘導)」の無視にある。人間は物体を見る際、小さな文字で書かれた警告文よりも先に、その形状や色彩から「何ができるか」を直感的に判断する。コロロというブランドが持つ「美味しいグミ」という強力なアフォーダンスが脳に深く刻まれている以上、どれほど明瞭に「食べられません」と記したところで、無意識の行動を完全に抑制することは不可能に近い。
国民生活センターが2025年度に公表した「食品に酷似した生活用品による誤飲事故調査」の報告書によれば、こうした製品による事故の約4割が、認知機能が低下した高齢者や、文字を読めない乳幼児によるものだった。2026年、日本の超高齢社会はさらに深化し、家庭内での製品管理が個人の注意義務(自己責任)だけでは限界に達していることを、以下のデータは如実に物語っている。
食品酷似製品に関するSNS言及数と誤飲・誤食相談件数の推移(国民生活センター・自社調べ)
法的空白とグローバル・スタンダードの乖離
現行の日本の法体系において、食品を模倣した非食品、いわゆる「フードミミック製品」のパッケージデザインそのものを直接的に規制する法律は存在しない。医薬品医療機器等法(旧薬事法)は、化粧品の成分や効能、表示義務については厳格な基準を設けているが、容器の形状や色彩が「どれほど食品に似ているか」という点については、具体的な禁止規定を欠いている。つまり、中身が法的に安全なハンドクリームであり、パッケージに「食べられません」という警告が表示されている限り、どれほど菓子に酷似していても、販売そのものは合法となる。
この「法的空白」が、企業のマーケティング戦略における倫理的な暴走を許容しているとの指摘が強まっている。特に欧州連合(EU)との対比において、その遅れは顕著だ。EUでは、製品安全の基本原則として「デザインそのものが持つ危険性」を厳格に問う姿勢が定着している。かつての指令87/357/EEC(食品模倣製品指令)から、2024年12月に完全施行された「一般製品安全規則(EU) 2023/988」へと法的枠組みが強化された現在、EU域内において食品に見える非食品の販売は事実上不可能に近い。同規則は、警告ラベルの有無にかかわらず、製品の外観、匂い、色、包装が食品と混同されやすく、消費者が口にする危険性がある場合、その流通を禁止する権限を加盟国に与えている。
対して日本では、あくまで業界団体の自主基準やモラルに委ねられているのが現状である。今回の事例は、SNSでの「バズり」を狙ったインパクト重視の企画が、この自主規制のタガを容易に外してしまう現実を浮き彫りにした。2026年現在、米国ではトランプ政権下での規制緩和が進む一方、クラスアクション(集団訴訟)のリスクが企業への強力な抑止力として機能している。日本は、欧州のような厳格な事前規制もなければ、米国のような事後の懲罰的賠償リスクも低いという、まさに安全管理における「空白地帯」にあると言えるだろう。
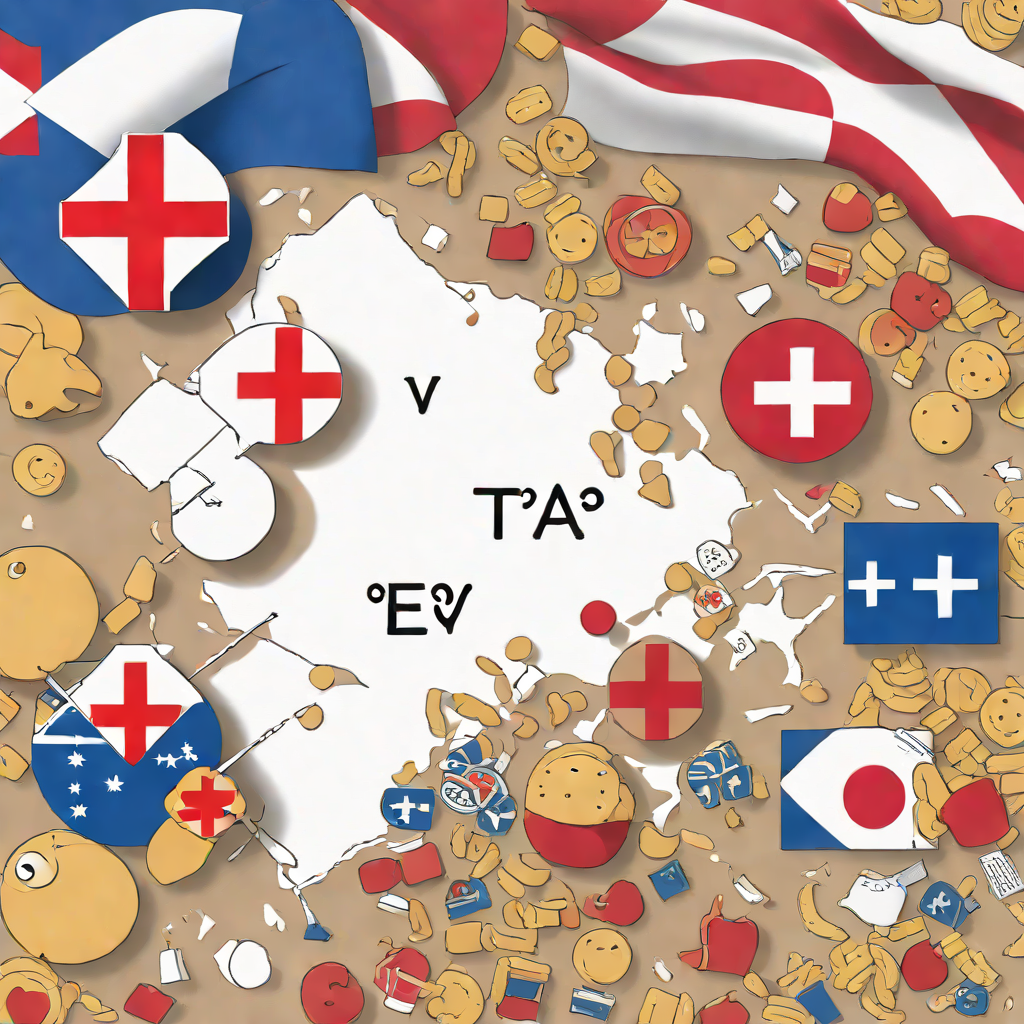
マーケティングの再定義:安全こそが最大のブランド価値
「話題性」という麻薬のような魅力に、企業の倫理観が蝕まれていないだろうか。食品メーカーと化粧品メーカーによる異業種コラボレーションは、市場に新鮮な驚きをもたらす有効な手法として定着した。しかし、今回の「コロロ」のパッケージを模したハンドクリームが引き起こした波紋は、その手法が孕む重大なリスクを浮き彫りにした。それは、消費者の脳に刷り込まれたアフォーダンスを軽視し、警告文という免罪符で安全管理を代替しようとする姿勢への根源的な問いである。
これからのコラボレーション商品に求められるのは、「意外性」と「安全性」の両立という高度なデザイン倫理である。ブランドのアイデンティティを保ちつつも、触覚や嗅覚、あるいは開封のプロセスにおいて、明確に「食品ではない」という違和感を演出すること。それこそが、プロフェッショナルなクリエイターの仕事であり、企業の品格を示す指標となる。
消費者の安全を脅かしてまで得るべき「バズ(話題)」など存在しない。安全という土台の上にしか、持続可能なブランド価値は築けないのだという原点に立ち返る時が来ている。一時の話題性よりも、長期的な信頼(トラスト)を選択すること。それこそが、2026年の市場で企業が生き残るための最大のマーケティング戦略となるだろう。